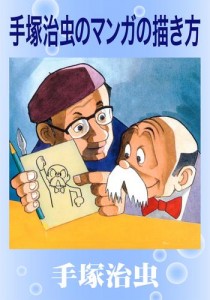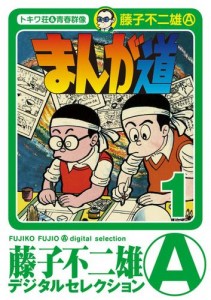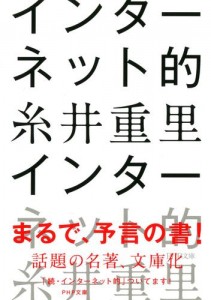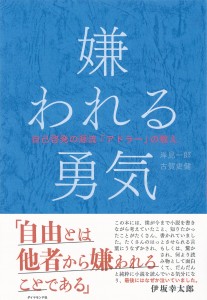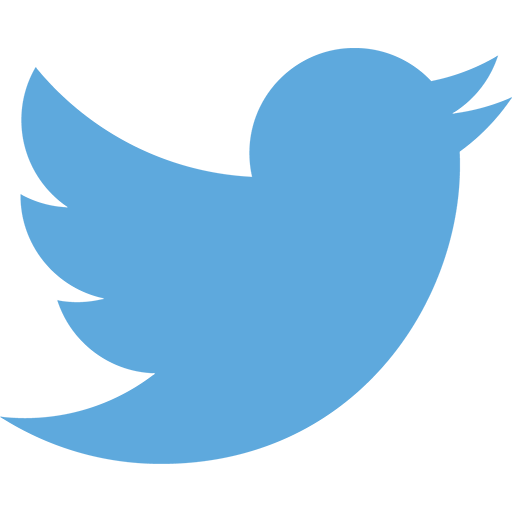「作家で居続けることはとても難しい。」
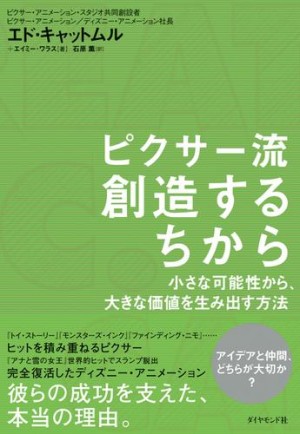
ピクサー流 創造するちから
ダイヤモンド社
2014/10/2
この本のあらすじ
1995年に「トイ・ストーリー」を公開し、続々とヒット作を生み出し続けるピクサー。高いクオリティと商業的な成功を継続させてきた仕組みとその物語を、創業者であるエド・キャットムル自身が語ります。チームのあり方や、それぞれの映画が生まれるまでの裏側など、詳細で豊富なエピソードは濃いものばかり。400ページにも及ぶボリュームですので、腰を据えてじっくりと向き合うのがよいかも知れません。
ピクサーの創業者、エド・キャットムルが「チームとして創造力を維持していく方法」について語っていきます。実は、作家になることはそれほど難しくありません。ただ、作家で居続けることはとても難しい。2冊目、3冊目と描いていくのに従い、心の中からわき上がってくるものを見つけにくくなるからです。継続的にクリエイティビティを保つためには、どうすればよいのか? 本書で語られるのは組織で行う場合での話ですが、自分の頭の中の思考法にも十分応用できます。たとえば、彼らピクサーのチームは「特別なアイデアはいきなり手に入らない」ということが分かっている。一度出した答えを、延々と直し続けていくのです。人間は、自分に対して簡単にOKを出してしまいがち。ピクサーが持っている「いいものができるまで直す」という体制は、漫画家にとっても重要なポイントです。
下記のストアから電子書籍を購入する
「作家を目指す人にもぜひ読んで欲しい。」
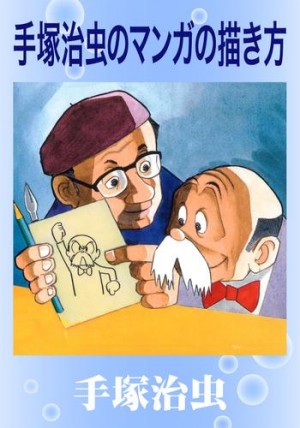
手塚治虫のマンガの描き方
手塚プロダクション
1977年
この本のあらすじ
「ひとつ、あなたもマンガをためしに描いてみませんか。」そんな誘いの一言から始まる本書は、漫画の神様、手塚治虫の神髄をとことん詰め込んだ漫画の指南書。漫画を描く時の道具の選び方、アイディアを生み出す方法、人物の動作の書き方から物語の構成まで、具体的なテクニックを余すところなく披露していきます。1977年のものが初版となる本書ですが、漫画の本質を捉えた内容は今なお全く古びることはありません。
この本は、漫画家だけではなく、作家を目指す人にもぜひ読んで欲しい。手塚治虫が、自身の手の内を一切隠さずに見せてくれます。本書では、漫画家としての心構えからテクニックまで、何もかもが語られている。特に、ここから学べる「現実をどのように観察するか」という目線は、作家にとって必要な資質です。とにかくたくさんの具体例が語られるのですが、「オーバーなアクションさまざま」という項では微妙に描き分けられたオーバーな仕草が20個以上のイラストで並びます。これらを一瞬で描くことができるようになり、その上でそれぞれの場面に相応しいものを選び、使い分けいくことが重要。ここからも、継続的にクリエイターでいるための姿勢が学べるはずです。
下記のストアから電子書籍を購入する
「孤独だと、高みにはいけない。」
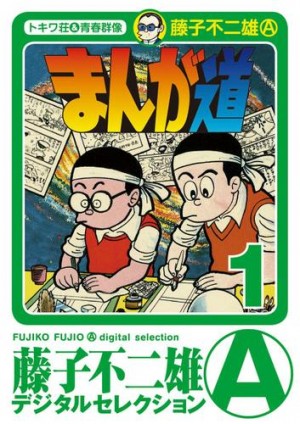
まんが道 <藤子不二雄(A)デジタルセレクション>
小学館
1970年
この本のあらすじ
藤子不二雄(A)の描く、漫画家ユニット「藤子不二雄」の半自伝的な物語。当初、「週刊少年チャンピオン」の付録的な存在として始まった『まんが道』ですが、最終的には40年以上の連載となる大作になりました。藤子不二雄の成長を描くだけでなく、手塚治虫とのエピソードやトキワ荘での暮しぶりなど、当時の漫画界を記録した資料としても価値の高い作品になっています。自分は本当は何が好きで、何を目指しているのか?ふたりの漫画家が織りなす青春物語は、読み手の胸の内にもきっと情熱の火を灯すはず。
漫画家は、知識を身につけ、情熱かけて、漫画に自分の人生をかけていくもの。『まんが道』や『青春少年マガジン 1978~1983』を読むと、そのことがよく分かります。彼らにとって漫画がどれほどのもので、人生においてどれだけ重要なのかが伝わってくるんです。漫画家を目指す人は、自分がそれだけ漫画を愛しているかどうかを知る必要がありますね。また、どちらの作品にも周りに一緒に努力をする人がいる、というのがポイントです。人間は、ひとりでは成長できません。確かに作品をつくるというのは孤独な作業だけれども、それ以外の生活の部分でも孤独だと、高みにはいけない。近くに切磋琢磨する人間がいて、そこで競い合っていくことで、別世界へと抜けていくことができるのです。
下記のストアから電子書籍を購入する
「今はどういう時代なのかを知っておく必要がある。」
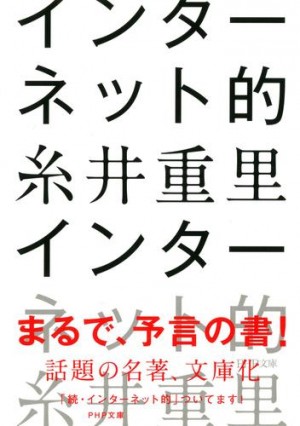
インターネット的
PHP研究所
2014/11/6
この本のあらすじ
私たちの生活の新たなライフラインとなった、インターネット。改めてその意味、役割を考えてみる時、『インターネット的』はうってつけの解説書です。ここで語られるのは、インターネットそれ自体だけではなく、”インターネット的""なるものたち。インターネットの登場で、社会や人間関係はどう変わったのか。その変化をつぶさに観察、予見していく内容となっています。1998年から休むことなく「ほぼ日刊イトイ新聞」を更新し、インターネットの成り行きを肌で感じてきた糸井重里。現代から未来まで、その見通しがスッとクリアになる1冊です。
これからは、漫画家や作家はスマートフォン上で自分の作品を発表していくことになります。なので、「インターネットとは何か」を、漫画家自身が理解して描いていかなければなりません。ただただ物語を書いていけばいい、ということではなく、今はどういう時代なのかを知っておく必要がある。それは、この『インターネット的』から学ぶのがいいでしょう。また、クリエイティブディレクターの水野学さんが書いた『センスは知識から始まる』もぜひ読んで欲しい。抽象的に語られがちな"センス"が、知識を蓄えていくことで磨かれることが分かります。一見、漫画や小説の外にあると思うことからも多くのことが学べます。インターネットと様々な物事を学んでいくことで、これからの新しい漫画が生み出されていくと僕は思っています。
下記のストアから電子書籍を購入する
「中途半端な状態では、何も成し遂げられません。」
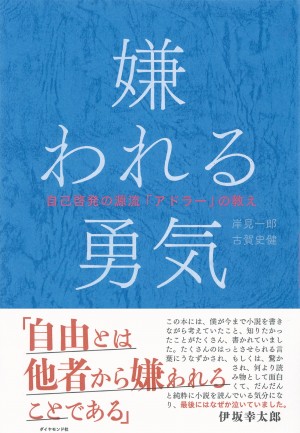
嫌われる勇気
ダイヤモンド社
2013/12/12
この本のあらすじ
フロイト、ユングと並んで「心理学界の三大巨頭」と呼ばれながらも、日本では周知されてこなかったアルフレッド・アドラー。彼の残した思想を、青年と哲人の対話形式まとめたのが本作です。「トラウマは存在しない」「人は怒りを捏造する」など、一見受け入れがたい哲人の言葉。青年は私たちの気持ちを代弁するかのように、哲人に食ってかかります。しかし、物語が進むにつれ、気づいていなかった、もしくは受け入れようとしていなかった自分の心の仕組みが露になっていく。多くの人々に共感と発見をもたらした、ベストセラーです。
『嫌われる勇気』は、老人と青年の対話形式で話が進んでいきます。生きることへの不安、悩みを吐き出す青年に対し、老人はそれらは全て自分の意識、意志によってコントロールできると説いていく。「みんなに好かれたい」と思ってしまったら、誰からも好かれることはありません。また、一部の人たちに深く愛されるということは、同じように一部の人から嫌われるということでもある。中途半端な状態では、何も成し遂げられません。これは、先ほどの「継続的に作品を生み出すのは難しさ」という話にも繋がります。「売れたい」と思うと、多くの人に読まれるために作品の角が取れて丸くなり、結局誰にも気づいてもらえなくなってしまう。漫画家として自分の作品を世に出していくためには、“嫌われる勇気”を持つことがとても重要なのです。
下記のストアから電子書籍を購入する
「物語は、偶然の産物ではないのです。」

ミステリーの書き方
幻冬舎
2010/12
電子化はされていませんが、『ミステリーの書き方』も学びの多い1冊。『手塚治虫のマンガの描き方』と同じように、多くのミステリー作家が自身の持つテクニックや考え方を披露してくれます。実は、物語とテクニックは別々の話ではありません。どういった表現を使うのか、細部まで考え抜くからこそたくさんの物語が生み出せる。物語は、偶然の産物ではないのです。電子化されている書籍では、『小説講座 売れる作家の全技術』もおすすめしたい。『ミステリーの書き方』が多くの作家のエッセンスをまとめたものだとしたら、これは大沢在昌というひとりの作家の”書き方”を深堀しています。常に読者に先を気にさせる必要がある、という点で全ての物語はミステリーだと言えます。漫画家を目指すのであれば、これらの本から学び、かつそれをきちんと実行に移すことが何よりも大事です。
下記のストアから電子書籍を購入する
取材協力:BACH
![[ booklista ] 株式会社ブックリスタ](https://www.booklista.co.jp/wp-content/themes/booklista_03/library/images/logo.svg)