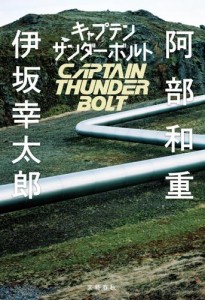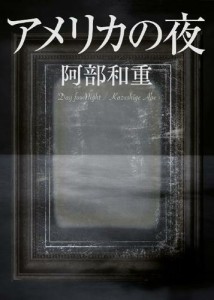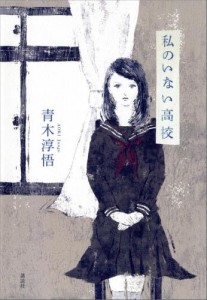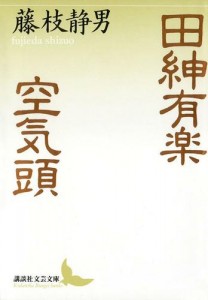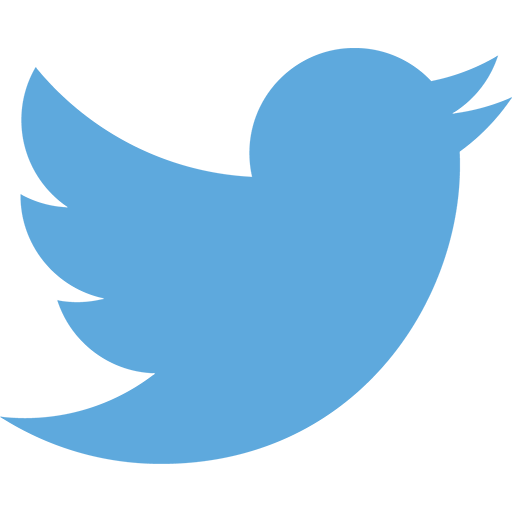「エンタメと純文学のトップ作家が本気で書いた作品」
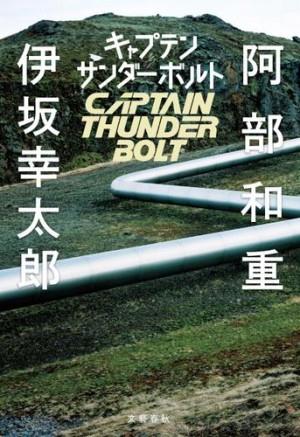
キャプテンサンダーボルト
文藝春秋
2014/11/28
この本のあらすじ
かつて、少年野球のチームメイトだった相葉と井ノ原。それぞれの道を歩んでいたふたりだったが、偶然的な出会いから再びコンビを組み、世界を揺るがす陰謀に立ち向かうこととなる。本書は、大人気作家の阿部和重と伊坂幸太郎による合作書き下ろし。魅力的なキャラクター、テンポ良く進む展開など、ふたりの持つ魅力が見事に溶け合った作品に仕上がっている。
『キャプテンサンダーボルト』は、エンタメと純文学のトップ作家が本気で書いた作品です。読者の方の中には、「作家は自分の思いのままに筆を走らせている」と思っている人もいるかもしれません。しかし、意外に感じるかもしれませんがエンタメと純文学、両方ともにテクニックやアイデアが必要なんです。本作を読めば、彼らが決してテクニックをバカにしてないことが分かります。一生懸命、愚直に工夫を盛り込んでいくことで、面白い作品が生まれる。そのことを証明している小説です。現在世に出ている作品の中の、ひとつの極北として読めるはず。でも逆に、「これではダメだ!」「こういうアイデアは古い!」という風に反発して、そこから新しいストーリーやキャラクターを生み出す人が現れるきっかけになるのもいいですね。エンタメと純文学、どちらを目指す人にも読んで欲しい1冊です。
下記のストアから電子書籍を購入する
「阿部さんは、一文字あたりの”アイデア量”がとても多い人。」
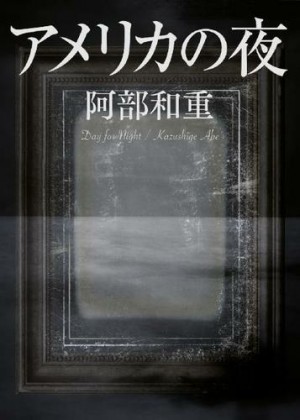
アメリカの夜
コルク
この本のあらすじ
中山唯生は映画学校を卒業するも、就職はせずに一人暮らしを続けるひとりの青年。そんな生活を送りながらも、彼は自分を「特別な存在」だと信じていた。あえて回りくどく書かれた言い回しや、小説の語り手が冷静に自分を批評する”自分自身”であったりと、取っ付きにくい印象も受ける本書。しかし、一度そのリズムに身を任せてしまえば、新しい読書体験の虜になるはず。
『キャプテンサンダーボルト』を手がけた伊坂幸太郎さんと阿部和重さん。彼らが素人の時代、編集者もいない状態でひとりで書き上げた作品はどんなものなのか?それを知るのも、非常に参考になるはずです。『アメリカの夜』は阿部和重のデビュー作ですが、すでに読んでいて圧倒されるぐらいの創意工夫が凝らされています。僕は編集者として多くの作家の原稿を見てきましたが、一目瞭然なんです。阿部さんは、一文字あたりの”アイデア量”がとても多い人。読み手に想像力を持ち出させるんですね。まだ名前が知られていない時に、自分の書いたもので人を面白がらせるというのはすごいことです。完成度が高く、新人の作品という感じはしないのですが、「デビューするためには、あれぐらい頑張らなければいけないんだ」と感じるためにも、手に取ってみてもらいたいです。
下記のストアから電子書籍を購入する
「ここには彼のすべてが詰まっている」
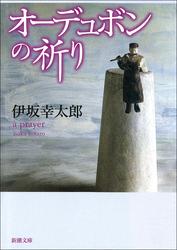
オーデュボンの祈り
新潮社
2003/12/1
この本のあらすじ
気がつけば、荻島という見知らぬ島にたどり着いていた伊藤。彼はそこで未来を予知できるカカシに出会うが、翌日にはそのカカシはバラバラ死体となって発見される。自分の死を止められなかったカカシの謎を解くべく、伊藤は島の調査を始めていく。絶対に嘘しかつかない画家、殺人を許された男など、独特の魅力を持つキャラクターたちからも目が離せない。
伊坂さんのデビュー作は『オーデュボンの祈り』ですが、ここには彼のすべてが詰まっている、と言うことができるかも知れません。この作品で提示された問題に、その後伊坂さんは技術を増し、丁寧に取り組んでいっているように思います。”小説がうまくなる"というのは、物語にグラデーションをつけられる、レイヤーを分けられるということでもあります。主人公やメインストーリーといったレイヤーはくっきりと表に出し、それ以外の要素はうまく背景に織り込ませる。キャラクター造形や会話に伊坂さんが工夫を凝らしているのは分かりやすいのですが、その他のちょっとした場面にもたくさんのアイデアが込められているんです。熟練した書き手になった今、彼がどこにこだわっているかは気づきにくいかもしれません。でも、デビュー作では比較的分かりやすくその”うまさ”を感じられると思いますよ。
下記のストアから電子書籍を購入する
「言葉はまだ、新しいことを表現できるのかも知れない」
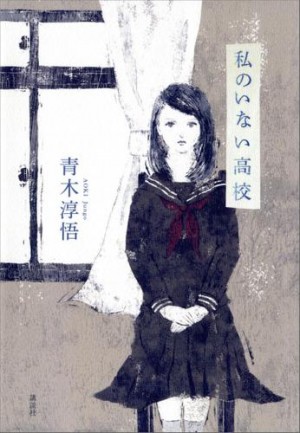
私のいない高校
講談社
2011/6/14
この本のあらすじ
ある学校の、普通の日常を切り取った青春小説。しかし、読み進めていくうちに、この小説は本当に”普通の日常"しか描いていないことに気づく。学内で起こることがただ淡々と記述されていくこの小説は、タイトルの通り主人公が存在しない。学級日誌のように紡がれる物語から、普遍的な学園生活を浮かび上がらせる異色な作品。
今、特に純文学の中で、現代の最高峰に当たるんじゃないかと思わせる作家が青木淳悟です。デビュー作の『四十日と四十夜のメルヘン』が新潮新人賞を受賞し、この作品も三島賞を受賞している。純文学の世界では大きく評価されているのですが、まだまだ一般的には知られていないんですよね。はじめてこの作品の原稿を読んだ時は、「生涯忘れないんじゃないか」というぐらいの衝撃がありました。とにかく新しいし、この作品について言葉にできないんです。彼の小説を読んで、「言葉はまだ、新しいことを表現できるのかも知れない」と感じました。今の若い方々がこの”新しさ”に刺激を受けてもらえれば、さらに純文学の新しい地平がこじ開けられていくはずです。
下記のストアから電子書籍を購入する
「文学って、もっと自由なもの。」
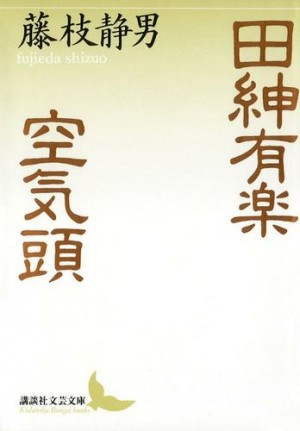
田紳有楽 空気頭
講談社
1990/6/10
この本のあらすじ
「田紳有楽」と「空気頭」という2つの中編から成る本書。どちらも藤枝の私小説であるが、その世界はとことん荒唐無稽で、幻想的。「田紳有楽」では池の水底に沈む自我を持った茶碗たちが語り出し、「空気頭」では序盤は病床の妻を描きつつも、突如自身の妄想を繰り広げるパートが挿入される。私小説の枠を超えた藤枝独自の世界を堪能できる1冊。
藤枝静夫は戦後の純文学作家で、医者でもあった「知的」な小説家です。だけれども、彼の描く物語は実にはちゃめちゃなんです。「田紳有楽」では茶碗がキャラクター化していて、水中から空へと飛んでいく。さらには、ぐい飲みと金魚が恋に落ちるんです。純文学は、「人の心の動きをつぶさに捉えて、人間関係のあわいを描くもの」とか「時代性、歴史を踏まえて書かれる」といった思い込みがありますが、それだけではないと思うんですよね。文学って、もっと自由なもの。皆が分からないこと、気づかないことを盛り込んで驚かせるのも、小説の役回りだと思うんです。そして、その中にきちんと思想性がある、ということが大事。なんだか縮こまっていると感じた時は、この本を読んで自分の枠を打ち破ってみてはいかがでしょうか。
下記のストアから電子書籍を購入する
「現在の作品だけをインプットしていても勝負には勝てません。」
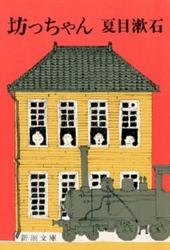
坊っちゃん
新潮社
1950/2/2
この本のあらすじ
大学を卒業後すぐに数学教師として四国の小学校に赴任した主人公。都会育ちだったために、田舎での生活は周りと衝突してばかり。しかし、持ち前の負けん気と無鉄砲な気質で、不公平な事柄に真正面から立ち向かっていく。言わずと知れた夏目漱石の名作だが、滑稽な人物描写や色恋沙汰などエンタメ色が強く、はじめて触れる漱石作品としてもうってつけ。
現在流行している小説を読むのもいいのですが、若いうちはとにかく古典に触れることをおすすめします。古典というのは、決して"古いもの”ではなく、いつの時代に読んでも面白く読める普遍的なものです。もちろん、流行の作品を読むことも大事ですが、それは後からでも大丈夫。それに、現在の作品だけをインプットしていても勝負には勝てません。小説でも、漫画でも、音楽や映画でも、本当に面白いものがクラシックとして残っている。それらは、ただ単純にすごく面白いんですよね。夏目漱石の『坊っちゃん』も、実はとても「漫画」っぽい。先を知りたくなるようなプロットで、ひとりひとりのキャラも立っている。冒頭の主人公が2階から飛び降りるシーンも、無鉄砲なキャラクター性を効果的に見せていますよね。古典は、自分のアイデアの源になってくれるもの。時間があれば、ぜひがっつりと古典を読みふけってみてください。
下記のストアから電子書籍を購入する
「いくら素晴らしい感覚を持っていても、人に分かりやすくするためにはテクニックが必要。」

定本 映画術 ヒッチコック・トリュフォー
晶文社
1990/12/1
エンタメ映画の巨匠として評価されていたヒッチコックですが、大衆向けの作品だと少し揶揄もされていました。しかし、晩年のインタビューを読めば、そこにどれだけの技術が費やされていたか、彼がいかに本当のアーティストだったのかが分かるんです。いくら素晴らしい感覚を持っていても、人に分かりやすく伝えるためにはテクニックが必要。どこに照明を当てるか、俳優にどんな表情をさせるか、どのように編集して組み立てるか… 彼には引き出しがたくさんあり、なおかつ創造力も持ち合わせていました。小説は映画と違い、言葉という道具だけで面白さを表現しなければいけません。テクニックが必要なのは映画も小説も同じですが、言葉は誰もが使えるものだから気づきにくいんですよね。言葉という道具を磨くためには、たくさんの作品を見て、たくさん考えて、たくさん気づかなければいけない。そのことを教えてくれる1冊です。彼の映画も、ぜひ見てみてください。
下記のストアから電子書籍を購入する
取材協力:BACH
![[ booklista ] 株式会社ブックリスタ](https://www.booklista.co.jp/wp-content/themes/booklista_03/library/images/logo.svg)