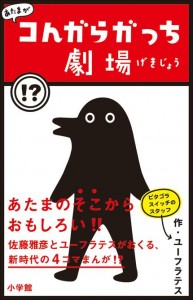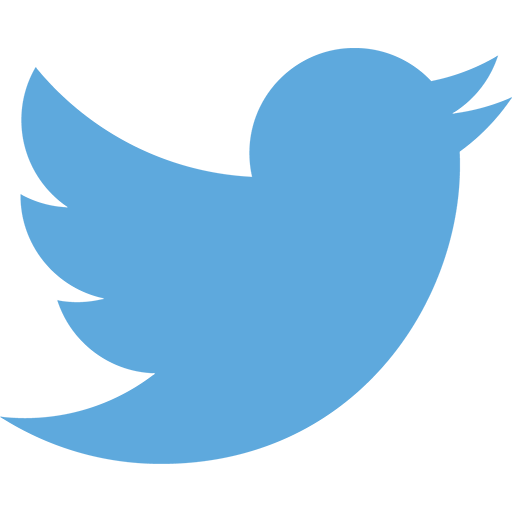「機械で同じことをやろうと想像してみて欲しい」

時速250kmのシャトルが見える~トップアスリート16人の身体論~
光文社
2008/7/20
この本のあらすじ
スポーツをアスリートの身体や精神について語るのではなく、アスリートの身体を取り巻く「環境」に焦点を当てて、アフォーダンス理論を実践の面からとらえた一冊。陸上選手にしか語れない「地面」、水泳選手にしか語れない「水」を中心など、生態心理学で「アフォーダンス」と呼ばれる「環境」の意味に、アスリート16人のインタビューを通じて肉薄する。
先日、カフェで奥にあった席に座ろうとテーブルの隙間を通り抜けようとした時、「あ、ちょっと狭いな」と思って少し体を横にして通り抜けたことがあった。この時私は、隙間を見ただけで普段自分自身では見ることができない自分の大きさと比較して、「まっすぐ歩いて通り抜けられる幅かどうか」を瞬時に判断していたということになる。そんなこと当たり前と思われるかもしれないが、機械で同じことをやろうと想像してみて欲しい。かなり複雑で高度な空間認識の処理を行っていることが分かると思う。日々生活するというのは、こういった体を動かすための処理を、瞬時に繰り返し続けているということでもある。では、もしこれがスポーツ、しかもオリンピック等の世界レベルのトップアスリートだったら、どれほど高精細な処理をしているのだろうか。この本は、その驚くべき実態がアスリート自身の口から語られている非常に貴重なインタビュー集である。
下記のストアから電子書籍を購入する
「私たちが意識している枠組みを次々と壊してくれる。」
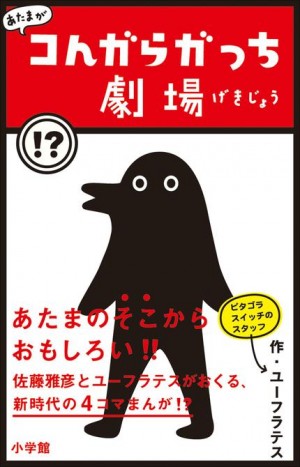
あたまがコんガらガっち劇場
小学館
2009/3/22
この本のあらすじ
「ピタゴラスイッチ」などで知られる佐藤雅彦とユーフラテスがおくる、新時代の4コマまんが。 いるかともぐらがこんがらがってできた生物「いぐら」が、旅をしたり、ごはんを食べたり、道に迷ったり…。新アイディアがいっぱいの絵本。論理的だけどかわいくて、密度が濃いけれどのんびりしていて、繰り返し読んでしまう魅力にあふれている。
初めて居酒屋で日本酒を頼んだ時、店員さんが枡に入ったコップに注いでくれるわけだが、コップから思いっきり溢れさせる注ぎ方をされ、「コップには溢れないようにぴったり注ぐものだ」という自分自身の前提がガラガラと崩れ落ちて、何故かとても興奮した記憶がある。私たちは無意識の内にあらゆる物事に関して枠組みを決め、その中で物事を見てしまう。だからこそ、一度自分で勝手に決めてしまった枠組みを自分で壊すのはとても難しい。多くの人が「枠組みに囚われない見方」を難しいものと感じているのは、おそらくこういった理由からである。しかし、一度枠組みを壊すことができれば、私たちは「枠組みの壊し方」や「壊れた時の快感」を学ぶことができるし、少しずつ自分の力で壊せるようになってくる。この本は漫画という表現手法を使いながら、私たちが意識している枠組みを次々と壊してくれる。読めばきっとあなたも、新しい枠組みの壊し方を学べるはずだ。
下記のストアから電子書籍を購入する
「私たち人類がこれまで積み重ねてきた知恵の結晶であり、財産」
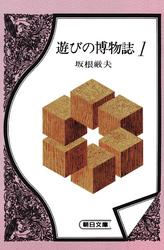
遊びの博物誌 1
朝日新聞出版
1985/5/20
この本のあらすじ
おもちゃ、パズル、からくり人形から、エッシャーの作品やかくし絵など、芸術家から科学者まで古今東西の「遊びの仕掛人」たちが繰りひろげる不思議の国のページェント。人間の自由な発想が生んだ愉快な遊びの数々を紹介し、読者を創造と発見のワンダーランドへといざなう。錯視・錯覚の不思議まで古今東西の「遊び」を紹介するビジュアル版。
錯視や鏡のように、「何故か変に見えてしまう不思議なモノ」に子供も大人も夢中になるのは、昔も今も変わらない。この本では、古今東西様々な遊びやゲーム、玩具(またはその原型のようなもの)を取り上げ、その裏にある科学の考え方や知覚のトリックを一つずつ分かりやすく紹介している。不思議なモノの裏には不思議に見える理由があり、それらはこの世界では「科学」と呼ばれている。本書で紹介されている遊びの数々は、私たち人類がこれまで積み重ねてきた知恵の結晶であり、財産だ。このような形でまとめられたものが今は絶版になっしまっているが、電子書籍であれば今すぐに読むことができる。是非4冊セットで手に入れて、読んでみて欲しい。続刊として、『遊びの博物誌 2』『新・遊びの博物誌 1』『新・遊びの博物誌 2』がある。
下記のストアから電子書籍を購入する
「人間の行動を扱っている分野全てに知覚の問題が関与してくる」

ファスト&スロー
早川書房
2012/11/25
この本のあらすじ
我々の直感は間違ってばかり?意識はさほど我々の意思決定に影響をおよぼしていない?心理学者ながらノーベル経済学賞受賞の離れ業を成し遂げ、行動経済学を世界に知らしめた伝統的人間観を覆すカーネマンの代表的著作。2012年度最高のノンフィクション、待望の邦訳。
みなさんも、数百円のモノを買うために複数の店を周って価格を入念に比較する一方で、コンピュータのような数十万円するものを買う際には、数百円の違いのためにわざわざ複数の店で価格を比較することなく即決してしまうといった経験があると思う。このように、私たちは頭では分かっていても、ついつい合理的ではない経済行動をとってしまうことがある。しかしその行動の裏には秩序やメカニズムがあることがわかってきた。本書では、人間の非合理的な経済行動についての新しい考え方である「行動経済学」という分野について、様々な事例を交えながら分かりやすく紹介されている。一見知覚と経済学は全く関係ないように見えるかもしれないが、読んで頂ければ、人間の行動を扱っている分野全てに知覚の問題が関与してくることが分かると思う。
続刊『ファスト&スロー 下』
下記のストアから電子書籍を購入する
「読後、きっと世界の見え方がガラリと変わる」

まなざし
ボイジャー
2014/7/1
この本のあらすじ
DOTPLACEで菅俊一が連載していたコラム「まなざし」が電子書籍化されている。「読むこと」「書くこと」とそのまわりに潜む日常のちょっとした違和感を、シンプルな言葉で丁寧に読み解いていく12編の「まなざし」。電子書籍版ならではの追加テキストも収録。イラストレーター・Noritake氏による描き下ろしイラストも見どころ。
私たちは日々の生活の中には、様々な知覚のエラーが溢れている。エラーを放置せず丁寧に観察し考えることで、普段見過ごしていた人間の驚くべき知覚能力について思いを馳せることができる。知覚のエラーに気づくことで、私たちは「当たり前」の世界認識から脱出して、未知なる驚きに溢れる世界の真の姿を見ることができる。本書には、みなさんが普段の生活の中でそうした気付きを得るためのヒント、12篇が収められている。読後、きっと世界の見え方がガラリと変わるような体験をして頂けると思うので、是非読んでみてもらいたい。
下記のストアから電子書籍を購入する
取材協力:BACH
![[ booklista ] 株式会社ブックリスタ](https://www.booklista.co.jp/wp-content/themes/booklista_03/library/images/logo.svg)